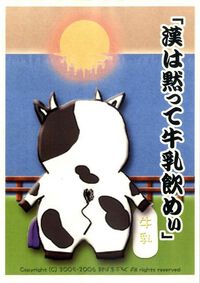2022年07月17日
干しいもづくりの作戦会議。
昼から宮地嶽神社参道の島屋で、干しいもづくりの作戦会議。
まずは、干しいもづくり研修@さつま町の報告。
次に茨城などなどで買い集めた干しいもを食べ比べしながら、
どんな干しいもを目標とするのか、
その製造工程をどうするのか、
議論を行いました。
で、今のところの結論は次のとおり。
〇 目標とする干しいも
・ 透明感のある明るい濃い黄色。
・ 表面はさらりとして、手で持ってもベタつかない。
・ 甘く、柔らかく、しっとりねっとりした食感。
・ 形状は角切りまたは丸干し。
○ 工程
・ デンプンの糊化を促進するため、
洗ったサツマイモの両端を切り、
水にひと晩浸けて水を吸わせる。
・ 食味向上及びデンプン糊化固定のため
糖を多く産生する必要があるので、
デンプンを分解するアミラーゼが働く時間を
できるだけ長く確保するよう、蒸し工程は弱火で2時間。
・ 蒸しあがったサツマイモは熱いうちに厚めに剥皮し、
釣り糸を張った道具でスライスする。
なお、丸干しの場合はスライス不要。
また、工程を減らせる「皮付き」が売れているため、
商品化を検討。
・ 最適な乾燥時間及び温度が不明であるため、
条件を変えて試験を行う。
○ 栽培
・ サツマイモのなかにできる「シロタ」は
干しいもの品質を落とすため、
イモが肥大する9~10月の土の乾燥防止対策を行う。
・ 皮つき干しいもの場合は、皮の見た目が重要であるため、
コガネムシや線虫対策が重要。
う~む、先は長いなぁ。
Posted by 朝倉2号 at 14:00│Comments(0)
│宗像・地島応援団