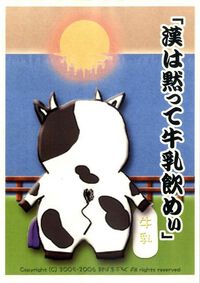2022年08月20日
干しいもを試作しました。
本日は地島応援団副団長、
宗像市にある佐藤さんの事務所で干しいもの試作。
使用したのは紅はるか、昨夜から水につけました。
鍋には4リットルの水、蒸し器に芋を並べ、弱火で蒸します。
弱火にしたのは「甘い干しいも」にしたいから。
干しいもの甘さはデンプンが分解されて産生した
麦芽糖の量によるものです。
この分解を行うアミラーゼは
65℃から80℃で働くということですので、
その時間をできるだけ長く確保することで麦芽糖が増えて
甘い干しいもになるはずなのです。

蒸しあがりの判断はいもに楊枝を刺して行います。
とりあえず2時間蒸して、
丸干し用の小さないもを取り出しましたが、
平干し用の大きないもは楊枝にちょっと抵抗があったので、
さらに30分、追加で蒸しました。
アミラーゼが働く温度帯は既に通過しているので、
追加で蒸すときは強火です。
30分追加して楊枝を刺すとスッと通ったので、
蒸し工程はこれで終了。
蒸しあがったいもは、まず、両端を切り落とし、
包丁を芋に直角に当てこそげ落とす感じで皮をむきます。

皮をむいたいもは、つき台(スライサー)で
厚さ8ミリにスライスします。

スライスしたいもは乾燥機で乾燥させます。
どれくらい時間がかかるか不明なので、
とりあえず50℃、6時間に設定。

6時間では食感がいまいちでしたので、さらに1時間追加。
乾燥工程を7時間で終了しました。
<まとめ>
・ 圧力鍋で加熱したものに比べ甘さが増しており、
弱火でじっくり加熱する方法は間違いない。
ただ、平干しのねっとり感不足は
火のとおり具合が甘かったのが原因と考えられる。
水が沸騰するまでの時間を設定するなど、
「じわじわ加熱」と「しっかり加熱」を両立させる
火加減と水の量を確認する必要がある。
・ 丸干しが粉っぽくなった原因を特定する必要。
丸干し用のいもは蒸し工程を2時間で終了したため、
火の通し方が甘かった可能性があるが、
追加過熱した平干し用のスライスが終了するまで
むいたいもを室温で放置したので、
その際に糊化したデンプンが老化した可能性も考えられる。
・ スライスする際にいもが崩れ、
商品化に耐えられないものが発生した。
スライスする際のいもの方向が、
切り落とした端からあてる「縦」がいいのか、
それともいもの腹からあてる「横」がいいのか、検討が必要。
・ 乾燥機から取り出した直後は表面が乾燥していたが、
すぐにラップでくるむと
水分が表面に付着することがわかった。
商品化する際は冷めるまで包装しない方がよいと思われる。
・ 今回は、蒸し工程に2時間半、乾燥工程に7時間、
その他、準備や片づけを含めると11時間を要した。
さらに冷めるまでにかかる時間を考えると、
12時間以上かかるものと考えられる。
夕方から乾燥機に入れ、朝、冷めてから取り出すなど、
生活時刻にあわせたオペレーションに落とし込む必要。
商品化まで、まだまだ長いなぁ。
次は地島産さつまいもでの試作かな。
できれば学生さんにも参加いただきたいですね。
<追記>
長崎県西海市で干しいもをつくっている
株式会社大地のいのちの干しいもづくり動画が
ものすごく参考になります。
※大地のいのち
Posted by 朝倉2号 at 20:00│Comments(0)
│宗像・地島応援団